

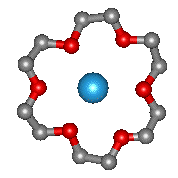
☆クラウンエーテルの話
最近このコーナーは長々と駄文ばかりで、当初の「美しい分子を紹介する」というコンセプトをやや外れていました。今回は美術館の名にふさわしく、分子の王冠をお目にかけましょう。あいかわらず文章は長いままですが。


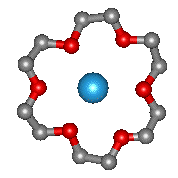
炭素(灰色)が2つ、酸素が1つの順で規則正しく並んで大きな環を作っています。王冠のようなその形からクラウンエーテルと名付けられました。環の大きさと酸素原子の数に応じて、左は12-クラウン-4、真ん中が15-クラウン-5、右が18-クラウン-6というような呼び方をします。
このクラウンエーテルが面白いのは、この環の中に金属イオンやアンモニウム塩のようなプラスの電荷を持ったイオンを捕まえることができる点です(輪の真ん中にある球がイオン)。酸素原子はマイナスの電気を帯びていますので、これらがプラスイオンを引きつけて捕えるのです。これを利用してイオン性の物質を有機溶媒の中に連れてくることができるなど、今までの化学の常識を打ち破る応用が可能になりました。このとき環になっているところが重要なポイントで、環を1ケ所切り開いた形のものに比べて1万倍も強くイオンを捕まえることがわかっています。
また、環が大きいクラウンは大きなイオンが、小さなクラウンには小さなイオンがフィットするという性質もあります。リチウム、ナトリウム、カリウムの順番でイオン半径は大きくなりますが、これらはそれぞれ12、15、18員環のクラウンに最も相性がよいことがわかっています。
クラウンエーテルがたくさんある場合は、2枚のクラウンで1つのイオンをサンドイッチのように挟むことができます。この場合本来の相手より大きめのイオンも捕まえることができます。これを利用して面白いスイッチ機能つきクラウンエーテルが合成されています。


2つのクラウンがN=N結合(中央の青いところ)を介してつながった形をしています。このN=N結合はふだん左のようにジグザグ方向に向いていますが、光を当てると右のようにコの字型に向きが切り替わり、結果として2つのクラウンが向かい合う形になります。すると2枚のクラウンでイオンを挟み込むことができるようになるため、左の状態より大きなイオンを捕えることができるようになります。いわば片手ではソフトボールくらいしか持てないものが、両手ならバスケットボールも持てるようなものです。つまりこの分子は光に応答してイオンの選択性が変わる「光スイッチクラウンエーテル」というわけです。
この他にもいろいろな機能を持ったクラウンエーテルが開発されていて、例えば下の化合物はナトリウムなどのイオンを捕まえると色が変化します。これを利用してイオンのセンサーなどが作れる可能性があります。

クラウンエーテルのイオン捕捉能力を上げる試みもなされています。新海らによって開発されたラリアット(投げ縄)クラウンは、その名の通りクラウンに長い鎖がついています。イオンがやってくるとこの鎖がさらに巻きついて、外れないように「固定」してしまうわけです。


ならばそちらも最初から環にしてしまえ、と2環式のクラウンを作ったのはフランスのLehnです。彼らはこれをギリシャ語で「隠す」を意味する「crypto」から「クリプタンド」と名付けました。

クラウンの環を二重にすることによってイオンをより強く捕まえるわけです。クラウンが「囲む」なら、クリプタンドは「閉じ込める」という印象です。そのイオン捕捉能は18-クラウン-6の10万倍にも及びます。
この他にも形や構成元素を変えることで様々な選択性を持たせたクラウンエーテルが合成されています。例えば酸素原子を硫黄に変えたチアクラウンエーテルは銀や水銀をつかまえますし、プラス電荷を持つ窒素原子を組み込んだ球状のクラウンは塩素のマイナスイオンを選択的に捕捉します。さらに大きな含窒素クラウンエーテルは、トリリン酸イオン(P3O102-)などの大きなイオンさえも包み込んでしまいます。



左から、チアクラウンエーテル(黄色が硫黄)、塩化物イオンを捕らえた球状クラウン、トリリン酸を捕らえたアザクラウンエーテル。
さらに凝った構造で、より高い選択性を持たせたものも開発されています。こうした種々様々なバリエーションを見ていると、クラウンエーテルという素晴らしい原理が見つかった後、数多くの人がそれぞれのアイディアを持ち寄り競い合って、この分野を大きく発展させたありさまがよくわかります。


左と右を見分けるクラウンエーテルもあります。D.J.Cramらによって合成された、ビナフチル骨格(左右の六角形の部分)を組み込んだクラウンエーテルです。野依らが開発したBINAPにも似た構造です。

アミノ酸には右手型と左手型(D体とL体という言い方をする。こちらを参照)があり、互いに鏡像の関係にあります。上のクラウンエーテルはL-アミノ酸とは結合できますが、D-アミノ酸とはビナフチル部分がぶつかってしまうため結合できません。これを利用して普通では難しい鏡像体の分離が可能になります。アミノ酸の効率的な分割は大きな需要があり、そのためこれはクラウンエーテルの最も重要な応用例の一つとなっています。
ちなみにクラウンエーテルは完全に人工の分子ですが、後に自然も似たような原理の分子を作り出していたこともわかりました。下に示すノナクチンなどがそれで、32員環の中にイオンを取り込んで運送する働きを持っています。

まず普通の研究者なら、そんなわずかな副産物は存在にすら気づかないでしょうし、見つけたとしてもその性質を追求してみようと考える人はごくわずかでしょう。偶然がもたらした発見とはいえ、それは単なるまぐれ当たりなどではなく、氏の慧眼はノーベル賞に値するものであったといえます(直接会社の利益にならないこの研究を続けさせた、デュポン社の懐の深さも賞賛に値すると思います)。
この時同時受賞したCram、Lehnらによってこの分野は大きく発展し、やがて分子認識、超分子化学といった一大ジャンルへと成長していきます。大きな進歩の種子は案外すぐそこらに転がっているのかもしれませんが、おそらく凡人たる我々はそんな種子をずいぶんと素通りしてしまっているのでしょう。最近ノーベル化学賞を受賞した白川・野依・田中三氏とも、大きな発見の元になったのは実験の失敗であったと口を揃えています。一流の研究者と凡人とを分けるのは、案外この辺のことなのかもしれません。